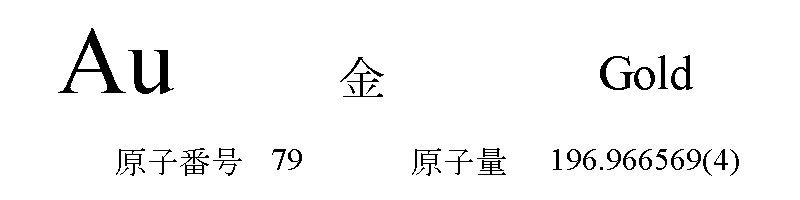性質および化学反応
黄金色のやわらかい金属元素で「こがね」と呼ばれるが、その色調は形状により異なり、直径20nm程度のコロイド粒子は赤紫色を呈する。延性および展性に富み、1グラムの金は2000m以上の針金に伸ばすことができ、金箔は厚さ10-5mmまで引き伸ばすことが可能である。薄い金箔は光を通し、透過光は青緑色である。最も重要な貴金属の一種であり、イオン化傾向は金属元素中最小で、酸およびアルカリに対する耐食性は高いが、王水および塩素水に溶解しテトラクロロ金(Ⅲ)酸を生成する。酸素の存在下ではシアン化カリウム水溶液に溶解しジシアノ金(Ⅰ)酸カリウムを生成する。高温ではハロゲンと直接反応し二元化合物を生成する。
6s電子の準閉殻性から電子親和力は金属原子としては最大であり、酸化数が-1であるCsAuのようなイオン性化合物も知られている。
元素記号Auはラテン語の金および光り輝くものを意味するAurumに由来する。オーラおよびオーロラも語源は同一である。水溶液中でのイオン化電位は金属単体中最も高く、+1.85 V (Au+/Au)を示す。
| 王水との反応 |
Au + 4HCl + HNO3 → H[AuCl4] + NO + 2H2O |
| シアン化カリウム水溶液との反応 |
4Au + 8KCN + O2 + 2H2O → 4K[Au(CN)2] + 4KOH |
 金の単体
金の単体
自然界における存在
金は安定で酸化されにくいため、自然界ではほとんど単体の自然金の形で産出する。石英中に微粒子の金が存在するものが多い。このような鉱石が風化し川を流れ下るに従い金粒子が互いに付着しあい大きな粒子に成長したものが砂金である。砂金は現在でも日本各地の河川に少量存在しており、まったく採取できない河川のほうがむしろ少ないという。これらの自然金は常に銀を数%〜数十%含む自然合金であり、エレクトラムと呼ばれる。南アフリカおよびロシアが主な産地であるが、世界的には広く分布する。日本国内でも鹿児島県の菱刈金山は世界最高の品位を誇る鉱石が産出する。世界有数の火山国である日本は江戸時代前期まで主要な金産国であった。
地殻の岩石中での存在度は低いが、広く薄く分布しほとんどの岩石に微量の金が検出されるという。一方、隕鉄中には約1 ppm含まれ、地球中心部の核にもこの程度含まれているものと考えられる。金鉱石はこのような地球の中心部に存在する金が硫黄などと錯体形成することにより地上まで運搬されたものが起源であるかも知れない。
 石英上の自然金 カリフォルニア産
石英上の自然金 カリフォルニア産
工業的用途
最も重要な用途は宝飾用である。合金中の金含有量は24分率で表され、純金は24金であり、宝飾用には18金がよく用いられる。酸化皮膜を生成しないことから電気接点および電子部品の配線などに用いられる。またインクによる腐食に強いため14金または18金が万年筆のペン先に使用されている。
金は錆びず希少価値があることから、物の価値の尺度として古くから貨幣として用いられてきた。最初は砂金がそのまま取引に使用され、古代ギリシャでは圧印貨幣が、日本ではたたき伸ばした判金が用いられるようになった。19世紀頃から金地金が貨幣価値に直結する金本位制が各国で採られていたが、1971年のニクソンショック以降は金地金と通貨は切り離されることになった。
 |  |
| 小判金・分金 | 金貨 |
主な化合物
化合物中では金原子の酸化数は+1,+3をとることが多い。
| AuCl |
塩化金(Ⅰ) |
Gold(Ⅰ) Chloride |
| K[Au(CN)2] |
ジシアノ金(Ⅰ)酸カリウム |
Potassium Dicyanoaurate(Ⅰ) |
| H[AuCl4] |
テトラクロロ金(Ⅲ)酸 |
Tetrachloroauric(Ⅲ) Acid |
| K[AuCl4] |
テトラクロロ金(Ⅲ)酸カリウム |
Potassium Tetrachloroaurate(Ⅲ) |
 テトラクロロ金(Ⅲ)酸
テトラクロロ金(Ⅲ)酸
|