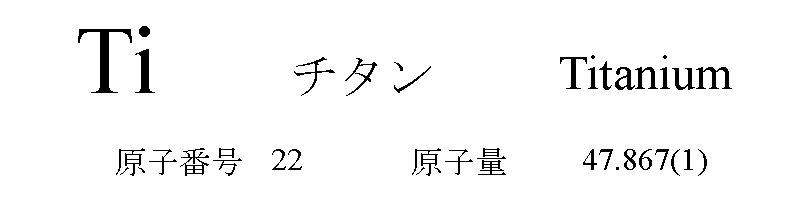性質および化学反応
銀灰色の金属元素であり、表面に薄い酸化皮膜を形成するため錆は内部まで進行しない。しかし、イオン化電位は低く -1.63 V (Ti2+/Ti)で、酸素との親和力も強く高温では空気中で酸素および窒素と反応する。濃塩酸には水素を発生して溶解し、初期には2価の陽イオンTi2+を生成するが、すぐに酸化され青紫色の3価陽イオンTi3+になり、さらに空気酸化され無色の4価であるチタニルイオン[Ti(OH)2]2+になる。
| 酸との反応 |
Ti + 2H+ → Ti2+ + H2 |
| 2価イオンの酸化 |
2Ti2+ + 2H+ → 2Ti3+ + H2 |
| 3価イオンの酸化 |
4Ti3+ + 6H2O + O2 → 4[Ti(OH)2]2+ + 4H+ |
 チタンの単体
チタンの単体
自然界における存在
チタンは岩石中に広く普遍的に存在し、主な鉱物としては酸化鉱物である金紅石TiO2およびケイ酸塩のクサビ型結晶が特徴である楔石CaTiOSiO4がある。火成岩中では主にチタン鉄鉱FeTiO3として存在する。
アポロ11号が持ち帰った月の岩石中には数%のチタンが含まれており、地球の岩石と比較して含有量が多いが、この含有量異常は採集された場所によるものか、月全体の特徴であるかはよく判っていない。
 |  |
| 金紅石(ルチル) | 楔石(淡黄色部分) 別子山産 |
 チタン鉄鉱 四国中央市五良津山産
チタン鉄鉱 四国中央市五良津山産
工業的用途
単体金属は酸素および炭素との強い親和性のため酸化チタンをコークスで還元することでは得られず、まず高温でルチルにコークスおよび塩素ガスを反応させ四塩化チタンTiCl4を製造した後蒸留し、これをアルゴン気流中で800℃でマグネシウムで還元するという、クロール法により製造される。このため製造コストがかかり、存在量が多い元素である割には高価なものになり、かつては需要の大部分が軍事用であった。
鉄より軽くかつ機械的強度が強く、耐食性もあるため自動車、自転車のフレーム、めがねのフレーム、および金属としては熱伝導性が低いことから鍋およびコップなどの食器の材料に用いられる。生体内の拒否反応が少ないため、骨折時の固定ボルトおよび人工関節などにも用いられる。
酸化チタン(Ⅳ)は屈折率が高く、被覆力が大きいため白色顔料「チタン白」として用いられる。
| クロール法によるチタンの製造 |
| ルチルから四塩化チタンを製造 |
TiO2 + 2C + 2Cl2 → TiCl4 + 2CO |
| マグネシウムによる還元 |
TiCl4 + 2Mg → Ti + 2MgCl2 |
主な化合物
化合物中ではチタン原子の酸化数は+2,+3,+4をとることが多い。
| TiO2 |
酸化チタン(Ⅳ) |
Titanium(Ⅳ) Oxide |
| BaTiO3 |
チタン酸バリウム |
Barium Titanate |
|