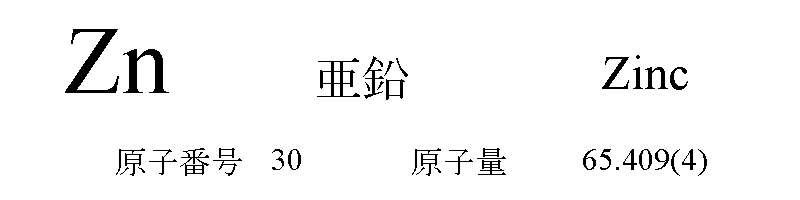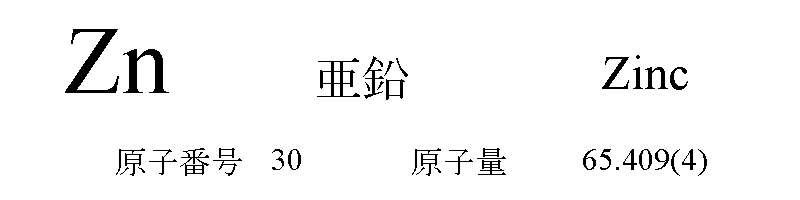性質および化学反応
青みを帯びた銀白色の金属であり、湿った空気中で徐々に酸化され白色の酸化物および塩基性炭酸塩などを生成し、次第に内部まで進行する。希塩酸および希硫酸にたやすく溶解して、水素ガスおよび無色の2価の陽イオンZn2+を生成する。Zn2+はマグネシウムにイオン半径が近いため、塩類の溶解度および結晶系が類似するが、Mg2+より錯イオンを形成しやすく、硫化物イオンと、より高い親和性を示す。
両性元素で、濃水酸化ナトリウム水溶液とも徐々に反応し水素ガスを発生する。酸化亜鉛および水酸化亜鉛も、酸およびアルカリ水溶液に溶解し、両性を示す。
| 塩酸との反応 |
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 |
| アンモニア水による沈殿反応 |
ZnSO4aq + 2NH3aq + 2H2O → Zn(OH)2(s)↓ + (NH4)2SO4aq |
Ksp = 4.1×10-17 |
| 過剰のアンモニア水との反応 |
Zn(OH)2(s) + 4NH3aq → [Zn(NH3)4]2+aq + 2OH-aq |
K = 1.49×10-8 |
| 過剰の水酸化ナトリウムとの反応 |
Zn(OH)2(s) + 2OH-aq → [Zn(OH)4]2-aq |
K = 1.16×10-2 |
| 塩基性条件下での硫化水素との反応 |
Zn2+aq + H2S(g) + 2NH3aq → ZnS(s)↓ + 2NH4+aq |
Ksp = 2.5×10-29 |
 亜鉛の単体
亜鉛の単体
自然界における存在
火成岩中ではケイ酸塩としてマグネシウムイオンの一部を置換しているが、亜鉛の鉱物として普通に見られるのは硫化物である閃亜鉛鉱ZnSである。閃亜鉛鉱は立方晶系(等軸晶系)であり、亜鉛および硫黄原子はそれぞれ4配位であるが、同質異像構造の繊維亜鉛鉱(ウルツ鉱)は同じく4配位で六方晶系である。
 |  |
| 閃亜鉛鉱 アメリカテネシー州産 | 菱亜鉛鉱 メキシコ産 |
工業的用途
亜鉛は蒸気圧が高いため、閃亜鉛鉱のコークスによる還元で製錬することは困難であり、単体として本格的に生産が始まったのは18世紀になってからである。ただしそれ以前から黄銅鉱と閃亜鉛鉱をコークスで同時に還元することにより真鍮(黄銅)は得られていた。亜鉛をめっきした鋼板はトタンと呼ばれ、亜鉛が酸化し電子を放出して鉄板の錆の進行を防ぐため、倉庫の屋根、バケツおよびちりとりなどに用いられる。またトタンと同じ原理で、船底に亜鉛版を犠牲電極として取り付け、錆の進行を防ぐ目的にも使用されている。銅との合金は黄銅、アルミニウムとはダイカスト合金をつくるなど、各種合金の成分として用いられる。
イオン化電位は比較的低く-0.7621 V (Zn2+/Zn)適度にイオン化しやすいため乾電池の負極活物質として用いられる。
酸化亜鉛粉末は軟膏、医薬品および粉おしろいとして用いられる。硫化亜鉛は屈折率が高く粉末は白色顔料として用いられる。
主な化合物
化合物中では亜鉛原子の酸化数は+2をとることが多い。
| ZnCl2 |
塩化亜鉛 |
Zinc Chloride |
| ZnO |
酸化亜鉛 |
Zinc Oxide |
| ZnS |
硫化亜鉛 |
Zinc Sulfide |
| ZnSO4·7H2O |
硫酸亜鉛七水和物 |
Zinc Sulfate Heptahydrate |
|