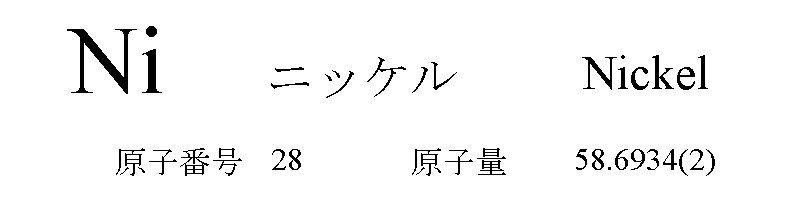性質および化学反応
銀灰色の金属元素であり、空気中では表面に極薄い酸化皮膜を形成し錆は進行しにくい。塩酸および希硫酸には極めてゆっくりと溶解し、水素および緑色の2価のアクアニッケルイオン[Ni(H2O)6]2+を生成する。希硝酸と反応し一酸化窒素を発生して溶解するが濃硝酸では不動態を形成する。微粉末を50℃で一酸化炭素と反応させると猛毒のニッケルカルボニル[Co(CO)4]を生成する。
ニッケルは強磁性を示し飽和磁気モーメントσsは20℃で54.39 [4π×10-4Wb·m]であり、磁石に吸い付けられられるが、鉄およびコバルトと比較すると磁性は弱く、キュリー点は358℃である。第4周期の8〜10族元素のFe,Co,Niは鉄族元素と呼ばれ、いずれも強磁性を示す。
1751年A.F.Cronstedtにより紅砒ニッケル鉱から新しい金属元素を単離し、銅鉱石のような外観にもかかわらず銅が得られなかったことから、悪魔を意味するKupfernickelをもとに元素名がつけられた。
| 塩酸との反応 |
Ni + 2HCl → NiCl2 + H2 |
| 一酸化炭素との反応 |
Ni + 4CO → [Ni(CO)4] |
| ニッケルイオンと当量のアンモニア水との反応 |
Ni2+aq + 2NH3aq + 2H2O → Ni(OH)2(s)↓ + 2NH4+aq |
Ksp = 5.5×10-16 |
| 過剰のアンモニア水との反応 |
Ni(OH)2(s) + 6NH3aq → [Ni(NH3)6]2+aq + 2OH-aq |
K = 4.9×10-7 |
 ニッケルの単体
ニッケルの単体
自然界における存在
隕鉄中には平均で7%程度のニッケルが含まれ、地球中心部の核にもこの程度含まれていると考えられる。主にマントルを構成すると考えられる橄欖岩中にはイオン半径が近いマグネシウムの一部を置換して0.2%程度のニッケルが含まれている。ニッケルはニューカレドニアおよびカナダが主要な産地で、一般的に含ニッケル粘土といわれている鉱石は橄欖岩が風化し、ニッケル分が濃縮されたものである。橄欖岩中のマグネシウムとニッケルのケイ酸塩が残されたものが珪苦土ニッケル鉱(Mg,Ni)6Si4O10(OH)8である。ヒ化物としては紅砒ニッケル鉱NiAsが存在する。
 |  |
| 珪苦土ニッケル鉱 | 紅砒ニッケル鉱 カナダ産 |
工業的用途
最も重要な用途はステンレスなどのニッケル鋼であり、この場合ニッケルは鉄鉱石とともに製錬され、フェロニッケルとして原料に供される。純ニッケルはニッケルカルボニルを熱分解させるモンド法で製造され、さらに電解精錬により精製される。わが国の100円および50円硬貨など各国で使用されている白銅貨は銅25%およびニッケル25%の合金である。旧50円硬貨はニッケル製であった
ニッケルめっきは錆が進行しにくいため鉄鋼の防食用に行われる。オキシ水酸化ニッケルNiO(OH)はニッケルカドミウム電池の正極活物質として用いられる。
 ニッケル貨
ニッケル貨
主な化合物
化合物中ではニッケル原子は2価[Ni(H2O)6]2+として存在することが多い。
| NiCl2·6H2O |
塩化ニッケル(Ⅱ)六水和物 |
Nickel(Ⅱ) Chloride Hexahydrate |
| NiSO4·7H2O |
硫酸ニッケル(Ⅱ)七水和物 |
Nickel(Ⅱ) Sulfate Heptahydrate |
| [Co(CO)4] |
ニッケルカルボニル |
Nickel Carbonyl |
 硫酸ニッケル(Ⅱ)七水和物
硫酸ニッケル(Ⅱ)七水和物
|